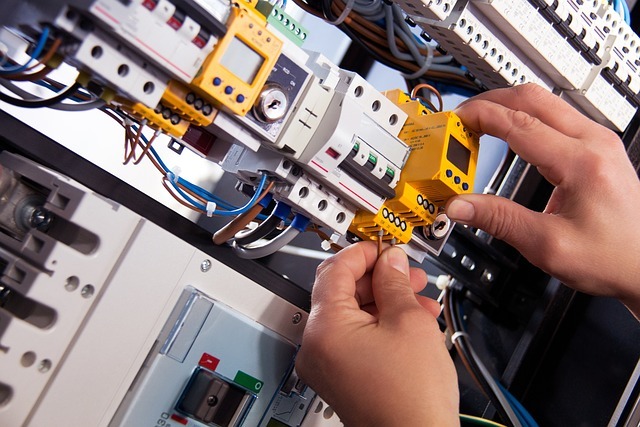産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは「産業廃棄物排出事業者から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とするために必要となる許可」のことを言います。
但し以下の場合は不要です。
1.自社の産業廃棄物を収集運搬する場合。
2.元請工事で産業廃棄物を発生させ自ら収集運搬する場合。
3.専ら再生利用の目的となる廃棄物である「専ら物」(再生利用される古紙、鉄くず(アルミ缶、古銅等を含む)、空き瓶、古繊維)を収集運搬する場合。
産業廃棄物とは
工業、商業、農業、建設工事などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類のもので、これ以外のものは一般廃棄物です。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃産
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん(ダスト類)
20.処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)
申請に必要な書類
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要
・運搬車両の写真(使用するすべての車両を斜め前方1枚・斜め後方1枚の計2枚ずつ撮影。)
・運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合に必要。)
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
・資産に関する調書(個人用)
・誓約書
申請にあたっては、申請書類のほかに、以下のような確認書類も必要になります。申請書類と合わせて準備しておきましょう。
申請者が法人の場合
・定款の写し
・履歴事項全部証明書
・役員全員及び5%以上出資している株主の住民票
・事務所の案内図
・登記事項証明書
・講習会修了証の原本
・自動車検査証の写し
・直近3年間の貸借対照表、損益計算書
・直近3年間の法人税の納税証明書 (その1)
申請者が個人の場合
・事業主の住民票
・事務所の案内図
・事業主の登記事項証明書
・講習会修了証の原本
・自動車検査証の写し
・直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)
・直近3年間の貸借対照表・損益計算書(青色申告の場合)
・直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)
・金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)
・市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)
・直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)
許可の要件
1.講習会を受講し試験に合格していること
「公益財団法人日本産業物処理センター」が実施する講習を受講し、試験に合格すること。
この講習は全国どこで受けても、全国すべての自治体に申し込むことができます。
但し、すぐに満員になりますので、急がれる場合は遠方の会場でも受講し、急がれない場合は近くの会場の開催を待つことになります。
2.経理的基礎を有していること
提出した書類により財務状況がチェックされます。
申請前直近3年間の決算書が、債務超過になっていないこと
財務内容によっては収支計画書や公認会計士、中小企業診断士等の作成した経理的基礎を有していることを説明した書類の提出を求められます。
3.適法かつ適正な事業計画を立てていること
事業計画とは、産業廃棄物が排出される場所・現場、産業廃棄物の品目・運搬量・形状、運搬方法などを踏まえて適切な業務内容や人員が整っている計画を言います。
4.収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物がが飛散したり、混ざらないようにする運搬車、運搬容器、運搬施設が確保できていること、運搬車両を使用する適切な権限や駐車場を確保できていることも要件となります。
5.欠格要件
・破産者で免責を受けていない人
・禁固以上の刑を受けて5年を経過していない人
・暴力団の構成員でないこと等
これらの対象者は、個人の場合、申請者、政令で定める使用人。法人であれば取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主となります。
申請書提出先
1.兵庫県
(1)政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合は当該「政令市」に申請
(1)以外兵庫県の各県民局ですが提出先の優先順位が以下の通りあります。
①~③の順に優先
①本店所在地(法人)、住所(個人)を担当する県民局
②兵庫県内の主たる営業所、事務所等の所在地を担当する県民局
③主な予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
※①~③いずれも神戸市市内の場合は神戸市を除く予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
-
|
受付県民局
(住所/電話番号)
|
本店等の所在地、事業計画において記載する予定排出事業場又は予定運搬先の所在地の市町 |
阪神北県民局 環境課 Tel(0797)83-3146
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局 環境課 Tel(079)421-1101
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町
天神木97-1
|
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局 環境課 Tel(0795)42-5111
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
西播磨県民局 環境課 Tel(0791)58-2100
〒678-1205 赤穂市上郡町光都2-25 |
姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町 |
但馬県民局 環境課 Tel(0796)12-1001
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
丹波県民局 環境課 Tel(0795)72-0500
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
丹波篠山市、丹波市 |
淡路県民局 環境課 Tel(0799)22-3541
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
洲本市、南あわじ市、淡路市
|
申請手数料 81,000円
手続きについては迅速丁寧に対応致します。
まずはお問い合わせください。
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士 西内佳彦事務所
TEL 0798(61)2935
2023年11月15日 09:50