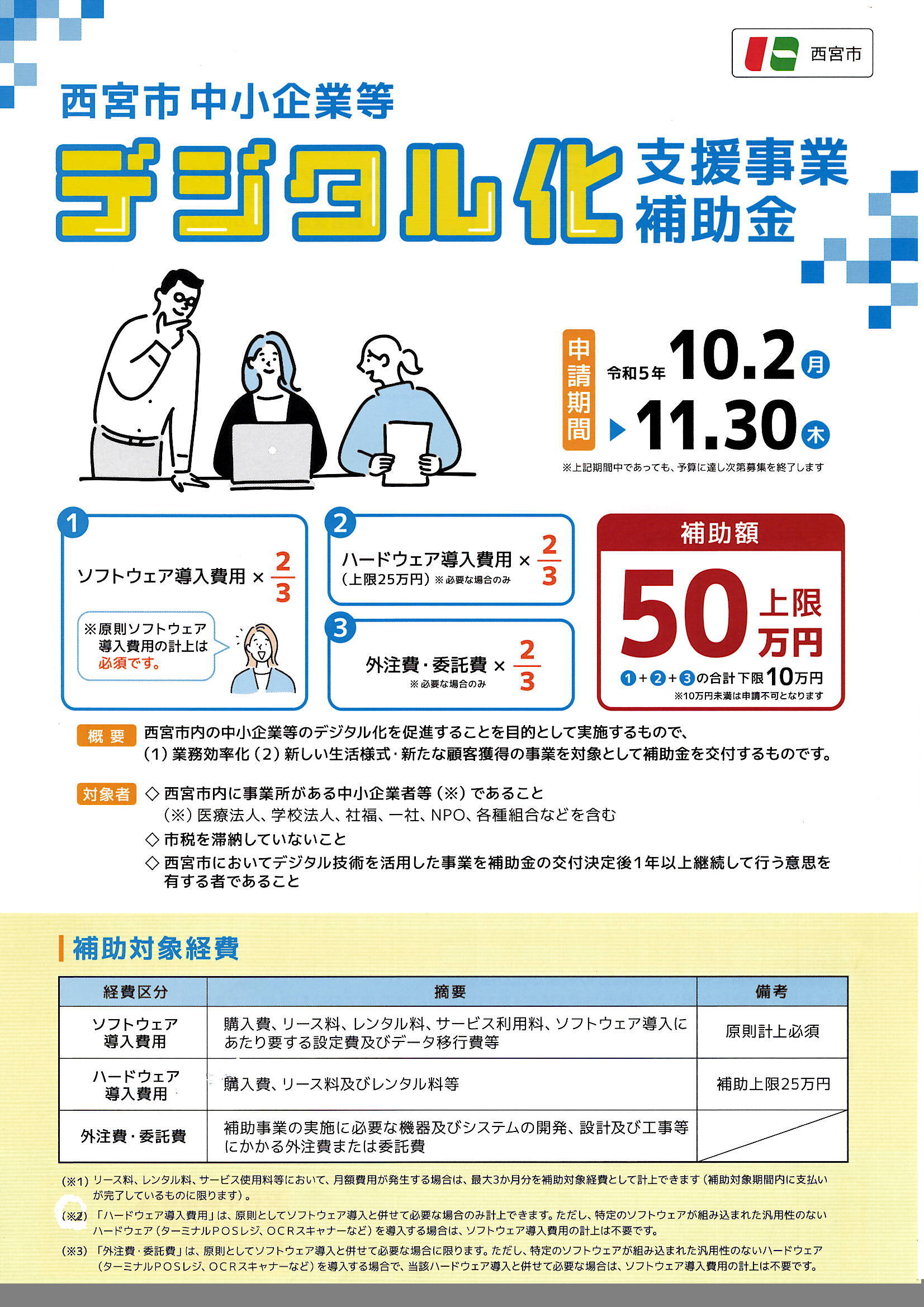西宮市の住宅に行う耐震改修工事の費用に対する補助金の明細は以下の通りです。
| 対象住宅 |
耐震診断の結果、安全性が低い(評点1.0未満)と判断された、昭和56年(1981年)5月以前に着工された住宅 |
| 対象者 |
上記住宅を西宮市内に所有する兵庫県民等 |
| 補助額 |
▶①耐震改修計画策定費補助・・・上限 20万円
▶②耐震改修工事費補助・・・・・上限¹100万円
▶③簡易耐震改修工事費補助・・・上限 50万円
▶④屋根軽量化工事費補助・・・・定額 50万円
▶⑤除却工事費補助・・・・・・・上限 40万円 |
| 申込期間 |
令和5年11月30日まで。予算が無くなり次第終了 |
*①②の長屋・共同住宅、マンションの申請は前年度5月中旬までに協議が必要です。
補助金申請時添付書類
①耐震改修計画策定費補助
(1)耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書(様式第耐震1-1号)
(2)住宅の所有者及び建築年が確認できる書類
(3)住宅の付近見取図
(4)耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書
(5)委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(6)区分所有の共同住宅の場合の書類
(7)申請者以外の所有権者の同意書
(8)確認書
②耐震改修工事費補助
(1)耐震改修工事住宅概要書(個表)(様式第耐震1-2号)
(2)補助金算定・精算書(様式第耐震2-1号)及び総工事費内訳書
(3)住宅の所有者及び建築年が確認できる書類※
(4)耐震診断報告書(様式第耐震3-1号)※
(5)課税証明書(所得証明書)の写し(発行可能な最新のもの)
(6)住宅耐震改修に係る図書※
(7)改修工事に係る建築確認済証の写し(改修工事(増改築含む)に建築確認が必要な場合のみ)
(8)改修工事を実施する事業者を確認できる書類
(9)耐震改修工事実績公表同意書(様式第耐震5-1号)(マンションの場合を除く)
(10)委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(11)区分所有の共同住宅の場合の書類
(12)申請者以外の所有権者の同意書
(13)確認書
※ 耐震改修計画策定費補助の実績報告と同時の場合は省略可
③簡易耐震改修工事費補助
(1)簡易耐震改修工事住宅概要書(様式第耐震1-3号)
(2)住宅の所有者及び建築年が確認できる書類
(3)課税証明書(所得証明書)の写し(発行可能な最新のもの)
(4)住宅の付近見取図
(5)改修工事を実施する事業者を確認できる書類
(6)耐震改修工事実績公表同意書(様式第耐震5-1号)
(7)委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(8)確認書
④屋根軽量化工事費補助
(1)耐震改修工事住宅概要書(個表)(様式第耐震1-4号)
(2)補助金算定・精算書(様式第耐震2-3号)及び総工事費内訳書
(3)住宅の所有者及び建築年が確認できる書類
(4)耐震工事事業計画書(様式第耐震3-2号)
(5)課税証明書(所得証明書)の写し(発行可能な最新のもの)
(6)住宅耐震改修に係る図書
(7)改修工事を実施する事業者を確認できる書類
(8)耐震改修工事実績公表同意書(様式第耐震5-1号)
(9)委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(10)瓦が土葺きであることがわかる資料
(11)確認書
⑤除却工事費補助
(1)住宅概要書(様式第耐震1-4号)
(2)補助金算定・精算書(様式第耐震2-4号)及び総費用内訳書
(3)除却する住宅の所有者及び建築年が確認できる書類
(4)除却する住宅の各階平面図及び耐震診断報告書(様式第耐震3-1号)
(5)課税証明書(所得証明書)の写し(発行可能な最新のもの)
(6)除却工事費用の見積書
(7)除却工事を行う事業者の建設業許可又は建設リサイクル法の登録を受けていることがわかる書類
(8)除却する住宅の付近見取図及び現況写真
(9)委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(10)確認書
以上西宮市HPより抜粋
補助金申請について上記の書類を添付しなければなりません。
設計事務所や工務店の事業者様で作成及び申請ができますが、行政書士でも対応できます。
多忙ななかで行政書士に依頼するのも一案です。
2023年05月09日 16:58